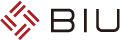見出し
⭕️婚活の落とし穴
マッチングサービス経由の婚活市場は2021年の予測では2026年までに2倍に膨らむと予測されています。
(2021年「マッチングアプリの利用状況に関するアンケート調査」三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
そして、行政も本腰を入れており、東京都の婚活マッチングサービス「TOKYOふたりSTORY」ではマッチングアプリの問題点を解消し、無償で結婚相談所に近いサービスを提供予定である。
しかし少子化問題が即座に解決するには繋がらないと私は予測する。
なぜなら「恋愛強者が得をするシステム」だからである。そして結婚と離婚を繰り返す恋愛強者が出てきて、シングルマザーが大量生産される可能性はある。
課題は選択が多すぎて1人に決められない心理です。
⭕️選択のパラドックス
シュワルツ教授の学説に基づけば、
「世の中の商品やサービスの選択肢の幅は、むしろ一定程度の抑えられた方が、消費者の心理的負担は少なく、かつ幸福度は高いことになる」
としている。2021年にニッセイ基礎研究所のレポートで、このジレンマは報告されています。
昭和以前の時代は、お見合いなどで数人程度の中から選択していました。今は数万人の中からお相手を選ぶだけで、かなり疲労します。
マッチングアプリだと詐欺師か?業者か?と疑いながら選ばなければなりません。
また社会的地位のあるハイスペックな男女だとSNSで恋愛内容を発信されるリスクも考えなければなりません。
また信用度の高い結婚相談所でも「活動する結婚相談所を比較して複数の無料相談をする」その結果、選ぶだけで疲れてしまうという声も聞きます。
⭕️行動経済学からみた婚活行動の問題点
牛窪恵さんの著書「恋愛結婚の終焉」では、行動経済学からみる、非合理的な婚活活動として3つ傾向をあげています。
◇1:【対象が多すぎて決められない、容易なリセット志向】
=決定回避の法則、選択のパラドックス、逆サンクコスト
l 人間は選択肢が多すぎる、途中で変えてもいい場合は、選ぶことがストレスになってしまう。
しかし自由度の少ない環境より多種多様な環境の方を選んでしまう傾向がある。
l 人間は金銭的・時間的コスト(サンクコスト)の重みを感じないと容易にリセットしてしまう。
◇2:【望む条件の「高望み」傾向、条件の肥大化】
=認知バイアス、ドレイクの方式
これはずらっと並んだ候補者がいると「もっと強気の水準で相手を探してみよう」と思うことです。
SNSで50代男性が20代女性と結婚した書き込みに真実を確かめもせず自分もできると思う心理も含まれます。
*ドレイクの方式の説明は文字数のため、割愛させてもらいます。
l 意思決定の主観的確率だけが上がってしまい「水準を上げるとマッチングしづらい」という現実がネットだと見えにくくなる現象と言われています。
◇3:【自分だけ抜け駆けしたくない、皆でハッピーになりたい】
=マッチング理論(GSアルゴリズム)、人気の序列化、嘘のインセンティブ
さらに加えてX世代、Z世代は悪目立ちを避ける傾向にあります。
SNSで容易に他人を叩ける状況のため抜け駆けを酷く恐れる傾向になっています。
そうすると自然と人気の序列化ができ「モテる男女同士がカップルになり、その他は婚活競争から降りてしまう」という現象になるのです。
⭕️「次があるかもしれない」の期待に惑わされないために
行政主導で構築された安価で幅広い選択肢があるケースでは、
「次があるかもしれない」
と容易に考えてしまう。
またタダであること行政サービスだと、どうしても嫌なことがあれば辞めてしまいがちである。
例えるなら公共のプールや体育館でのマシンの活用と同じ。
最大の課題は継続である。
そして「どうせタダだから、また始めればいい」と考える。1年程度の時間を経過して再開すると当然婚活偏差値は下がってしまうので、1回目に「次があるかもしれない」でお断りしたお相手が気になり、後悔する。そして遂に結婚にゴールインしても過去の恋人・お見合い相手と比較してしまう。
「たら・レバ」の思考サイクルに陥りがちである。
解決策として
「ジャムの法則」より人が選択する時の選択肢の数は7±2がベストと言われています。
この数値の間までに結婚相手を決めるのがベストと言われていますので頭の隅に覚えていだければ幸いです。